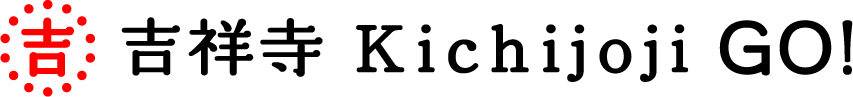吉祥寺駅北口から徒歩約10分。五日市街道沿いにある小さな公園。面積は1,719平方メートルです。
「緑を楽しむ交流の杜」をコンセプトに整備されました。遊具などはありませんが、夏になれば緑が生い茂り、子供たちの遊び場になっていたり、ベンチで休憩する人も多く、地域の憩いの場になっています。
また公園の片隅に長方形の大きな看板が立っています。
そこには「吉祥寺村のはじまり」と題して、五日市街道を挟んだ短冊状の区画整備の歴史が書かれています。
なぜ五日市街道沿いには細長く真っ直ぐに伸びる道が多いのか、その理由が分かります。
下記は全文引用したものです。興味のある方はご一読下さい。
吉祥寺村のはじまり
武蔵野市は、かつて4つの村でした。吉祥寺村、西窪(西久保)村、関前村、境村。
この四ヵ村をまとめて、武蔵野村としたのは明治22(1889)年のことです。さらに、昭和22(1917)年に、武蔵野市となり、今日に至ります。
明暦3(1657)年に江戸で大きな火事(明暦の大火)がありました。火元は、本郷丸山町のお寺で、振袖についた火が火事の元になったという話もあり、「振袖火事」とも言われています。
火事の炎は強い北風に煽られて、たちまち南方へ広がり、神田や日本橋、そして江戸城の天守閣も焼き、本郷元町(現在の水道橋の北側)にあった「吉祥寺」という大きなお寺や門前の人達の家も焼けました。
翌年、明暦4(1658)年にも大火があり、江戸の半分以上が焼失し、このときも「吉祥寺」は焼け、門前の人達も焼き出されてしまいました。この大事を「吉祥寺火事」といいます。
江戸城をも焼き払った大火により、水道橋の名刺(めいさつ)、「吉祥寺」を駒込の本郷本富士町に移し、門前の人達には江戸から遠く離れた野原の広がる牟札野(現吉祥寺)に土地を与えました。これにより、駒込の名手松井氏、浪士佐藤氏、旗本宮崎氏は五日市街道沿いに移住し、その西隣りには江戸の西の窪の城下町の井野氏が入植しています。
万治2(1659)年から移住が始まり、人々には五日市街道を挟んで両側に20間(約36m)、奥行き634間(約1140m)の同じ形の土地が分け与えられました。人々はまず、道沿いに家を建てその奥(北側又は南側)に畑を作り、しきれないさらに奥の方は山林として残しました。
そして山林から木材や燃料をとっていました。当時の短冊状の細長い土地の名残を、五日市街道に交わる今の道路に垣間見ることができます。

MAP
SNS
SNSでも吉祥寺情報を発信しています。
繋がりましょう。
発信者:高橋賢司
Webディレクター/吉祥寺 Kichijoji GO!運営
吉祥寺在住。吉祥寺の飲食店情報を中心に発信。ときどき西荻、三鷹、中央線、全国の美味い店
Instagram > X・旧Twitter > YouTube >